みなさん、こんにちは。30代会社員で現在1年間の育休を取得中の3児の父takatyです。
少年野球では、学年ごとに大会があるのが一般的ですが、特に小学3年生になるといわゆるジュニア大会が始まってきます。
チームの人数状況やレベルにもよりますが、徐々に試合が増えてくるチームも多く、我が家の長男(小3)が所属しているチームも段々と試合が増えてきました。
今回は、低学年における試合について、思うところや感じているところをお話していきたいと思います。
低学年の試合っていつ頃増えてくるの?
長男の所属しているチームでは、近隣市が参加する大会が複数あり、その中で、小学校3年生以下の区分もエントリーすることができます。
大会によってトーナメントだったりリーグ戦だったり様々で、複数の大会にエントリーしているとそれなりに試合数を重ねることになります。
しかも、3年生の夏以降に試合が組まれることが多く、急に土日どちらも試合とか、ダブルヘッダーになったりとか、今まで練習がメインだったのと比べたら大違いです。
それもそのはず、3年生の中盤以降になってくると、それなりに試合が成立するようなレベルになってくるチームが多くなってくるので、どのチームも夏以降に試合を組みたがるんです。
低学年の試合ってどんな感じなの?
低学年の試合は、「5回または70分」のように、イニングもしくは時間経過で試合終了となるルールが多いです。
また、1イニング5点交代や振り逃げなし、インフィールドフライなし等、大会によっては微妙にルールが異なることもあります。
ストライクが入らなかったり、守備では打球処理ができずに中々アウトにならなかったりしますし、盗塁なんてほぼ100%成功しますからね、選手たちの気持ちを考えても良いルールだと思っています。
試合の勝ち負けは二の次?
もちろん試合で勝った喜びや負けた悔しさを経験して、今後の糧にしてもらうことも大事だと思いますが、個人的には、低学年の試合は勝ち負けよりも「試合ってこんな感じなのか」というのを感じてほしいなと思っています。
そもそも野球のルールを完璧に覚えていない子どもも多いので、試合のプレーの中でルールや状況判断を覚えていったり、練習の時と違って、ランナーがいる中で守備をする緊張感や同じ年代の子どもが投げたボールを打つことを経験するだけで、試合をやった価値が十分あるといえるでしょう。
あとは、親目線としては、子どもが活躍してる姿を見れるだけで幸せなんですよね。
練習時間の確保をどうするか問題
このように試合がたくさん入ってくるようになると、当然ながら練習時間が確保できなくなります。
このバランスがとても難しいところで、試合ばかりでも技術向上がおろそかになるし、練習ばかりでは試合経験を積むことができない。
そうなると、やはり平日の自主練習をいかにやるかが重要になってきます。
長男も段々と試合が多くなってきて土日の練習時間が少なくなってきたので、家での自主練習用に置きティーを買いました。
ただ素振りをするよりも置きティーで実打できた方が良いと思い、少しお値段が高いですが長く使うものなので、奮発して買っちゃいました。
試合で打てなかったコースや苦手コースをイメージしてやることで、試合のフィードバックも兼ねた練習が可能になりました。
守備では、リバウンドネットがおすすめ。
室内でも室外でも、ちょっとのスペースがあれば壁当てのように守備練習をすることができます。やはり基本が大事ですからね、コツコツと積み重ねていくことでビッグプレーが生まれるのです。

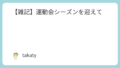

コメント