みなさん、こんにちは。30代会社員で現在1年間の育休を取得中の3児の父takatyです。
少年野球では、各チームの拠点である小学校や中学校が試合会場となることが多く、塁間の距離や様々なラインを引いて会場設営をする必要があります。
しかし、正確な距離やラインの引き方って、意外と野球経験者でも知らないこともあったりします(未経験の方であればなおさら)。
しかも、低学年(1年生~4年生)と高学年では、距離も変わってきます。
そこで、今回は、低学年(1年生~4年生)の塁間距離やラインの引き方について、解説をしていきたいと思います。
低学年用のグラウンドの寸法は?

- ピッチャープレートからキャッチャーまでの距離は14m
- 塁間距離は21m
- 二塁ベースはホームベースから29.69mで、一塁、三塁ベースの交差する点が二塁ベースの中心
低学年(1年生~4年生)では、高学年と比べて距離感が少し短くなるため、注意が必要です。
小学校などでは地面に目印が埋まっていることが多く、おおよその距離はわかります。練習ではおおよその位置でベースを置くなどして問題ないと思いますが、特に大会などの公式戦の会場となる場合は、メジャーを使ってしっかりと計測し、ラインを引かないといけません。
また、グラウンドによっては、花壇や草むらなどに入った場合にボールデッドにするためのラインを引くこともあります。グラウンドの状況をしっかりと把握しておくとスムーズに会場を設営することができます。
ラインの種類とまっすぐなラインの引き方

スリーフィートラインを引く際の注意点
スリーフィートラインは、一塁側のファールラインと平行に引くラインのことです。
バッターランナーがスリーフィートラインをはみ出して走ると、守備妨害を取られる可能性があり、その基準となる線です。
この線を引く際の注意点として、一塁線と完全に交差させずに少し空白を作っておくことです。
一塁線と完全にくっつけてしまうと、フェア、ファウルの判定がわかりにくくなってしまうからです。
なお、グラウンドによっては、平行線のみを引くパターンやコの字型にするパターンもあります。
ダートサークルを引く際の注意点
ダートサークルとは、野球場の本塁周辺にある直径約7.3m(少年野球では6.6m程度)の円形の土のエリアを指します。
多くの野球場は、ピッチャーマウンドと各塁付近が土で、それ以外は芝生になっていることが多く、ホームベース付近の芝生と土の境界線を明確化するために、ダートサークルが引かれています。
以下のことがダートサークルの役割です。
- キャッチャーやランナーがスムーズに動ける土のエリアを明確化。
- バント処理や本塁でのプレー時に足を取られにくくする。
- フェア/ファウルの判定基準になるわけではなく、主にプレーの安全性・利便性のための設計。
小学校などのグラウンドは全面土のことが多く、あまり意味のないように思われがちですが、バッターが振り逃げになった際に、振り逃げの意思があるかどうかを判定するために使われることがあります。
上手にラインを引くコツ
まずは、グラウンドのポイントを基準に寸法をメジャーで図ります。
特に、ファールラインは長い距離を引かないといけないので、ラインの目印となるロープがあると良いと思います。
ロープが設置できたら、あとはロープの上をなぞるように引いていくだけでまっすぐなラインを引くことができます。
ちなみに、ラインはラインカーを使って引くのですが、長い距離を引く際は四輪のラインカーがおススメです。
一方で、バッターボックスやネクストバッターズサークルなど短い距離や円のラインを引く際は、小回りの利く二輪ラインカーがおススメです。
まとめ
今回は、低学年(1年生~4年生)の塁間距離やラインの引き方について解説しました。
細かい部分は、各グラウンドや野球連盟によって変わるかもしれませんが、意外と知っているようで知らないのではなかったでしょうか?
次回は、バッターボックスの寸法についても解説しようと思います。
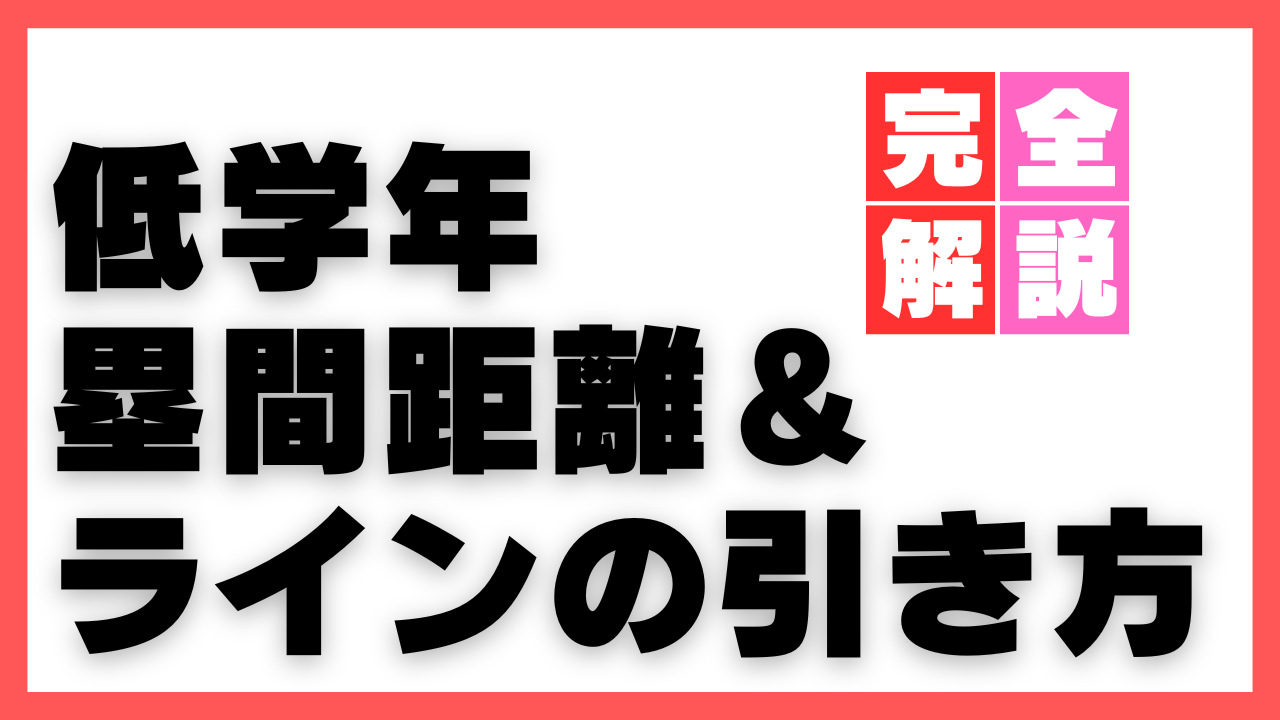


コメント